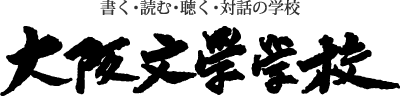第1回 5/20(月)夜・文章講座のご案内。
夜・文章講座
プルーストと小説の諸方法 Ⅵ ――眠れる女・その生と死のテーマから永遠なる芸術へ
講師 葉山郁生(作家)
◎内容
・第五篇『囚われの女』の「ママからの手紙」以前(第一部)
・課題=「代表的一日」の黄昏のモチーフ
今回の課題の例文として、プルーストの文章は省き、柳田国男の「かはたれ時」を掲げておきます。夕昏=かはたれ時は、光と闇の交錯、陰影が際立ち、この人とあの人、生者と死者、現実と幻想、過去と現在の境界が曖昧になります。ここの二重性を重ねた文章を意識して書いて下さい。
柳田国男「かはたれ時」
黄昏(たそがれ)を雀色時(すずめいろどき)ということは、誰が言い始めたか知らぬが、日本人でなければこしらえられぬ新語であった。雀の羽がどんな色をしているかなどは、知らぬ者もないようなものの、さてそれを言葉に表わそうとすると、だんだんにぼんやりして来る。これがちょうどまた夕方の心持でもあった。すなわち夕方が雀の色をしているゆえに、そう言ったのでないと思われる。古くからの日本語の中にも、この心持は相応によく表れている。たとえばタソガレは「誰そ彼は」であり、カハタレは「彼は誰」であった。夜の未明をシノノメといい、さてはまたイナノメといったのも、あるいはこれと同じことであったかも知れない。
私は今国々の言葉において、日の暮れを何というかを尋ねてみようとしている。加賀と能登ではタチアイといい、熊野でマジミというなども深い意味があるらしいが、それはなお私には雀色である。信州では松本の周囲において黄昏をメソメソドキ、少し北へ行くとケソメキともいって、暗くなりかかるという動詞はケソメクである。これも感覚を語音に写す技能と言ってよいと思うが、あの地方では人が顔を合せにくい事情などがあって、そしらぬ振(ふり)をして通って行くことを、ケソケソとして行くといっている。越中の山近くの町で、夕方のことをシケシケというのは、しげしげと人を見るというなどが元のようでもあるが、富山の附近の者は気ちがいのことをシカシカといっているから、最初はかえってシカとせぬことをシカシカといったのであろう。『曠野集(あらのしゅう)』の附句に、
何事を泣きけん髪を振おほひ
しかじか物も言はぬつれなさ
恥かしといやがる馬にかき乗せて
これなどにはまだ少し古い感じが遺っている。
尾張の名古屋などは、以前の方言は黄昏がウソウソであった。ウソはいつかも奥様の会で話したごとく、近世一つの悪徳と解せられるようになる以前、ほとんど今日の文芸という語と同じに、あらゆる空想の興味を包括していたことがあった。むつかしく言えば現実の粗材(そざい)、すなわちもう一歩を踏み込んでみないと、それを経験とも智識ともすることのできぬものの名であった。迂散(うさん)などという漢字を宛(あ)てようとした動機が、この言葉の中には籠っている。タチアイという言葉が夕方を意味したのも、この方からおいおいにわかって来るかも知れない。今でも取引所の中ではよく使っているが、タチアイは本来市立(いちだち)のことであった。仲間でない人々が顔を合す機会は、もとは交易の時ばかりであったゆえに、同じ用語をもっていわゆる雀色時の、人に気を許されぬ時刻を形容したのではなかったか。富山の町でも夕方をタッチャエモト、金沢ではまたイチクレとさえいっているのである。
地方の言語がおいおいに集まって来れば、もう少し説明がはっきりとすることと思うが、今でも黄昏がいかなる時刻であったかは、これだけの材料からほぼ推測し得られる。皆さんがあるいは心づかれないかと思うことは、人の物ごし背恰好(せかっこう)というものが、麻の衣の時代には今よりも見定めにくかったということである。木綿の糸が細く糊(のり)が弱くなって、ぴったりと身につくような近頃の世になると、人の姿の美しさ見にくさはすぐ現れて、遠目にも誰ということを知るのであるが、夕(ゆうべ)を心細がるような村の人たちは、以前は今少しく一様に着ふくれていたのである。見ようによってはどの人も知った人のごとく、もしくはそれと反対に、足音の近よるを聴きながら、声を掛け合うまでは皆他処(よそ)の人のように、考えられるのがケソメキの常であった。そうして実際またこの時刻には、まだ多くの見馴れない者が、急いで村々を過ぎて行こうとしていたのである。
鬼と旅人とをほぼ同じほどの不安をもって、迎え見送っていたのも久しいことであった。ところがその不安も少しずつ単調になって、次第に日の暮は門の口に立って、人を見ていたいような時刻になって来た。子供がはしゃいで還りたがらぬのもこの時刻、あてもなしに多くの若い人々が、空を眺めるのもこの時刻であった。そうして我々がこわいという感じを忘れたがために、かえって黄昏の危険は数しげくなっているのである。