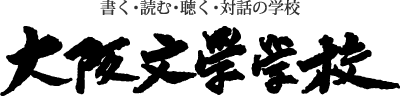第1回 夜・文章講座のご案内。
夜・文章講座
書くために読むⅤ――ドストエフスキーを生かす(番外篇)
講師 葉山郁生(作家)
第1回 11月16日(月)午後6時30分~
余儀なき生、不条理な人間
埴谷雄高短篇集(全集版等)から「意識」他(コピー配布予定)を解説
* * * *
課題=「埴谷雄高と小川国夫の間の一エピソード」を読んで、上記(余儀なき生、不条理な人間)の内容で、短編(その一部)を書いて下さい。タイトル自由
秋の期の葉山文章講座一回目用のエピソード文は次のとおりです。私が長期連載している文章の一部を抜き出してみました。埴谷雄高も病後にあり、小川国夫は三十代で、まだ無名の作家時代のことです。エピソードは、二字下げの部分です。
血を吐く病状の後、小川国夫は初めて、埴谷雄高の家を訪問している。埴谷・小川の往復書簡の第四信、小川側の「共存する二つの光」は、そのエピソードの回顧から始まる。
埴谷も台湾時代、結核を発病する。体験した病状の程度、時代の医療技術の差もあろう。埴谷は中年すぎ、この結核を再発させる。これが「近代文学」誌上、『死霊』四章での休筆となる。療養中、腹ばいになって、代表的な政治評論、文学評論を書き、私たちの世代の文学青年、政治青年は六十年、七十年代に読んで、大なり小なり影響を受けた。
…………
小川は自身の幼少期を振り返って「私は幼少のころから、病気の問屋といわれていた。疫痢、猩紅熱、結核、胃からの吐血、心臓弁膜症という次第だ」(『一房の葡萄』「治癒力)と述懐している。
吐血と心臓弁膜症は、六一年頃、小川三十四歳の二月以降のことで、一ヵ月ほど入院生活を強いられている。先に勝呂評伝でみたところの年月にあたっていて、この時期に書いたのが、「酷愛」「サラゴサ」であった。この前年、六十年安保の政治の季節、秋十月に東京を去るにあたり落魄の思いがなかったとは言えないだろうが、故郷藤枝に帰郷している。後にこの帰郷を起点に文学仲間との交流や、恋愛と病い中心に自伝小説『悲しみの港』が新聞連載されることになる。小説では、実生活と違い、妻子との話を除き、独身で孤高の文学青年として描かれていた。小川の実人生と文学の全体の流れの中でも、壊れそうになるほどに心の底まで降りた一つの転機に当たる時期だったのだろう。
埴谷雄高と小川国夫の往復書簡『隠された無限〈終末の彼方に〉』に、この頃、小川が初めて吉祥寺の埴谷邸を訪れたエピソードが回顧されている(小川国夫第四信「共存する二つの光」)。用のないのに急に押しかけて行った小川は、それ以来、何十回も訪問し、「いつも一様である埴谷家の応接間のたたずまいは今やたちどころ目に浮かびますし、私の第二の故郷と称んでもさほど誇張ではないほどになっております」と書き出している。当時、自分が胃から吐血し、心臓弁膜症と指摘されて不安だから、埴谷に病気の話をしたい、と申し出たという。埴谷は「病気の話をすべきだ、病気は人の心と心の紐帯となり得るから」と受けて、次のエピソードを自ら語り、小川は「貴方のこの話に、私は聞き惚れておりました」と書く。あれは埴谷一流のサービスだったのか、それとも自分に対するサービスであったのか、多分、後者に違いない、と、小川が言う話とは次のようなものだった。
歩くことが健康に必要だとは自覚しているが、そのためには当面の目的がないといけない、自分は〈意味もなく歩くこと〉ができなくなっている、しかし、ある時、全く理由もなく、飲み屋に行きたくなったことがあった、だから自分は、かなりの距離を歩いて、そこへ行った。知人は勿論、なじみの人もいなかったので、酒を注文して黙って一人で飲んで帰ってきただけだ。ただ今に忘れられないことは、そこで相客の一人の男と目が合ったことなんだよ。僕は腰のあたりに何かを感じて、気になったので目をそっちに移すと、相手も何かを感じていた様子で、こっちを見た。一瞬目を合わせた。僕は直ちに、その男の余儀なくされた人生経験の積み重ねを見て取ったと思ったんだ。その男もきっとそうだ。埴谷雄高の目に、あるよりは無いほうがよかった宇宙史を示唆した人生の重量を感得したに違いない。小川君、テレパシーを信じるかね。余分なことが解るというのではない、精髄が一瞬で解るのがテレパシーだろう、もしあそこでテレパシーが互いに働いたとすれば、僕は隠された理由によってあの飲み屋へ導かれたことになる、事前にその予感があったというべきなのだろうね。
人間の最大の幸せとは、人間に生まれないことだ、とある哲学者は言ったが、それは哲学者がこの世に生まれた上での逆説的言辞だろう。「未出現宇宙」を構想する埴谷も、そう言っていたし、見知らぬ二人がぱっと、目を合わす、このエピソードに出てくる男も、埴谷の分身のごとくである。目と目で一瞬、相手の心が読めることに、不条理に晒されることの多い人間どうしのそれでも生きてきた潔い共感がある。
人は出会うべきほどの人に、いずれ人生のどこかで出会う。埴谷とこの男と同じく「隠された理由」(それはいずれ、『悲しみの港』のように文学が表現させてくれるだろう)によって、小川は埴谷邸を訪れたのだ。
何一つできない、と「酷愛」の主人公は、自縄自縛の内界を抱いていた。埴谷が語る「余儀なくされた人生経験」には、埴谷の人生も、小川の人生も入っているだろう。小川が当時、思っていて、まわりにも語っていた、さっぱり先の見えない文士・小川の「難破船」のような航跡(『悲しみの港』の主題の一つ)を、埴谷は、充分、理解していて、自身の過去も重ね、深い深いエールを、初めて急に訪れた若い小川に送っていたことになる。
* * * *
・教材作品はできるだけ読んでおいてください。
・課題作(原稿用紙2枚《ワープロの場合、A4用紙をヨコにしてタテ書き印字》)を、講座日の3日前までに、担当講師宅へ郵送のこと。提出のあった作品をすべてコピーして、皆で読みあいます。(一般の方などで講師宅の住所がわからない場合は、事務局まで問い合わせてください)